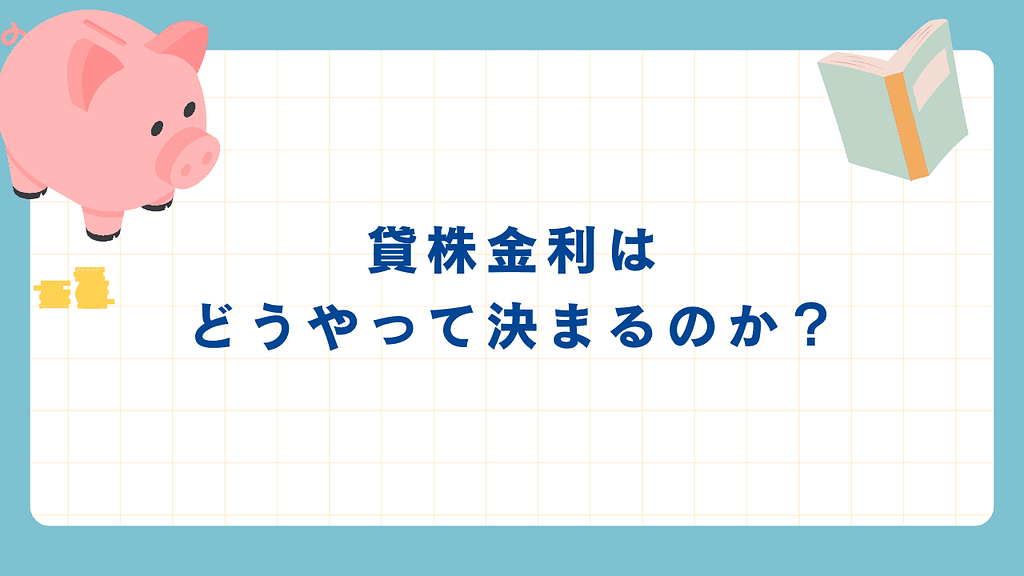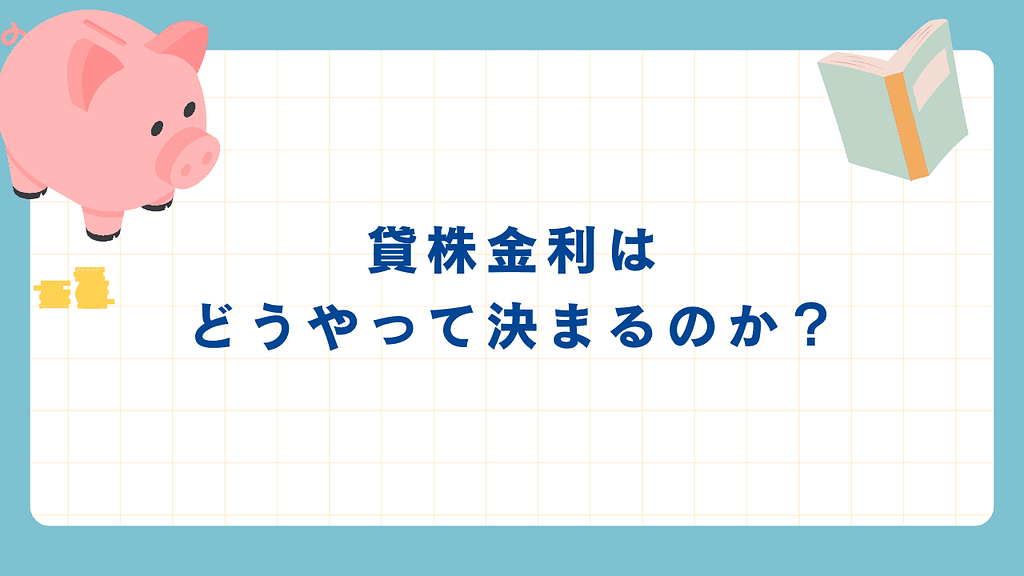 貸株金利はどうやって決まるのか?.png
16.1KB
貸株金利はどうやって決まるのか?.png
16.1KB
「貸株金利はどうしてこんなに銘柄ごとに大きな差があるのか?」、「貸株金利はグロース株は高金利で大型株は低金利なのはなぜか?」、「貸株金利はどうしてこんなに頻繁に変動するのか?」といった疑問を持った事はありませんか?その疑問を解消するには、貸株金利がどのように決まるのか知ることが必要です。
貸株の仕組み
貸株金利は当然ですが需給で決まります。
需給を知るために、まずは貸株の仕組みを確認しましょう。
下記図は貸株の仕組みを表す図です。
 株の貸出_貸株料_空売り関係図.png
40.3KB
株の貸出_貸株料_空売り関係図.png
40.3KB
上図の通り、我々が貸出した株は、証券会社からさらに外資系証券会社等を中心とした機関投資家またはその証券会社の利用者である一般投資家に貸出しされます。
機関投資家は自己勘定またはヘッジファンドの空売り用に株を借りる
機関投資家の中心は野村證券やゴールドマンサックスのような証券会社ですが、これらの会社は自己勘定での空売り用途もしくはクライアントのヘッジファンド等の空売り用途に株を借ります。
貸出元の証券会社と貸出先の機関投資家との貸株の取引は、市場参加者が参加するブルームバーグのコミュニケーションツールでやり取りが行われています(私がネット証券に在籍していたのは2010年代前半ですが、今も変わっていないはずです)。
市場参加者が参加できるブルームバーグのグループチャットのような機能で、株を借りたい機関投資家側から「xxxx の株ありませんか?」(通常英語のやり取り)といった感じで呼びかけがされ、それに貸出元の証券会社側が応えて取引を成立させるというやり方でした。
近年は一般投資家の一般信用売りの存在感が強まる
一般信用取引自体はかなり昔からありましたが、2013年から信用取引の制度が変わって、回転売買の資金拘束のルールが変わったり、近年では楽天証券の「いちにち信用」やSBI証券の「HYPER空売り」(俗にハイカラ)などのサービスも登場し、個人投資家の一般信用売りの規模が膨らみ存在感が増してきています。
高額な貸株料をなぜ負担できるのか?
銘柄によっては我々一般投資家が受取ることができる貸株金利が5%を超えるものもあります。
このような高金利の原資は空売りを行うヘッジファンドや機関投資家、一般投資家が負担する貸株料となります。
5%の金利と考えるとものすごく大きいと感じる人がいるかもしれません。
しかし、株式投資の株価の変動の大きさや、自己資金以上に取引できるレバレッジ効果を考えると、これくらいの負担を払ってでも空売りで儲けを出すことが出来ると考えている勢力が大勢いるのが実情です。
貸株の供給元は一般投資家の貸株だけではない
ここまで、貸株の需要サイドの話をして来ましたが、続いて貸株の共有サイドの話です。
もちろん貸株の供給は、一般投資家の貸株だけではありません。
一般投資家以外も大勢貸株をしています。先日、
GPIFが外国株の貸株を再開するというニュースが話題になっていましたが(なお、GPIFは国内株については貸株刷る予定が無いとのこと)、株式を長期保有するのであれば、貸株料の収入を得ることでリターンを少しでも向上させるのが常套手段です。
また、空売りされることは、
貸株のデメリットの記事で解説しましたが、流動性の向上や、市場効率性の向上という面でポジティブです。
大量に貸株をしている主体は、銀行や生損保などの金融企業、トヨタなど規模が大きく持ち合い株を持っている事業会社などが上げられます。
投資信託で運用される株式と信用取引の買残も貸株される
大勢の一般投資家の方が投資信託を買われたり、信用取引で株を買われたりしていると思いますが、実はこれらも貸株の供給元になります。
投資信託で運用される株は信託銀行経由で貸株されています。
そして、一般投資家が証券会社で信用取引で株を買った場合、その名義は株を買った投資家名義とはならず、証券会社の名義となります。
こうして証券会社名義となった信用取引買残の株を証券会社は貸株で運用するのです。
以上が、貸株金利が決定されるために知っておくべき、貸株の仕組みと需要と供給の説明でした。次回の記事でより具体的に「グロース株はなぜ貸株金利が高いのか?」について解説したいと思います。