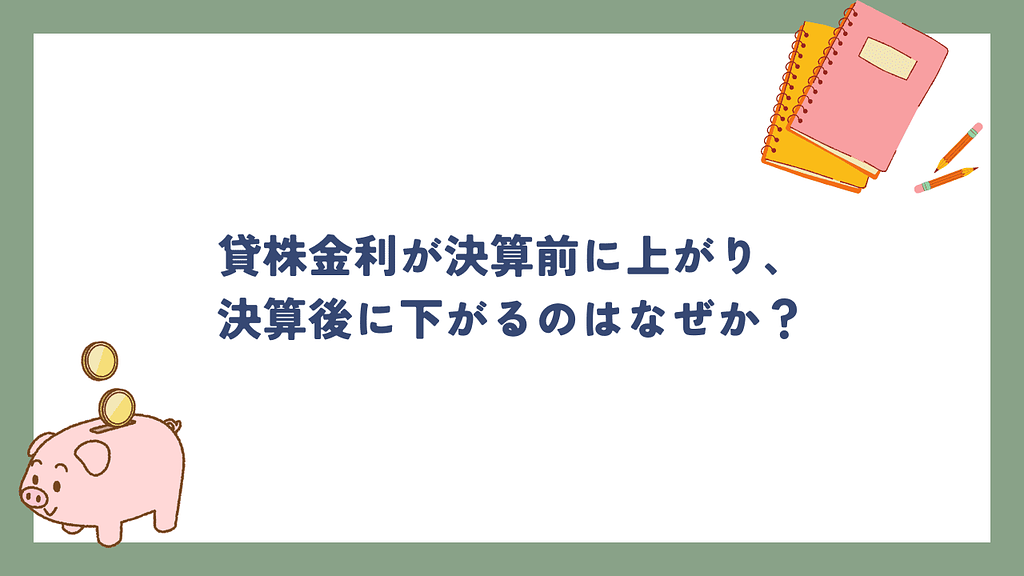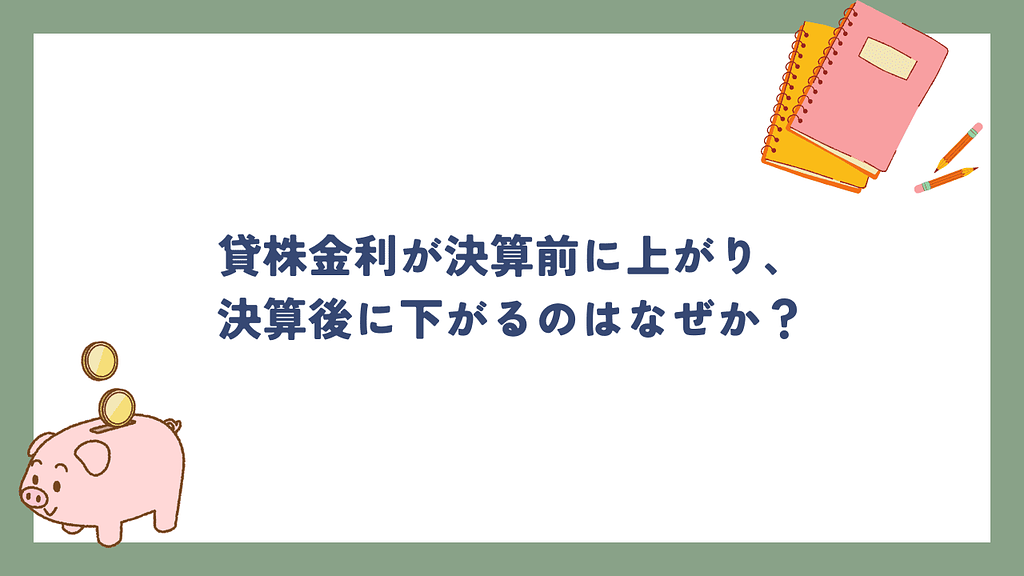 貸株金利は決算前に上がり、決算後に下がるのはなぜか?.png
20.2KB
貸株金利は決算前に上がり、決算後に下がるのはなぜか?.png
20.2KB
貸株金利は日々変動していますが、特に大きな変動をするタイミングがあります。それは決算のタイミングです。実際に貸株金利の推移をグラフで確認してみましょう。
 楽天証券_グロース株平均貸株金利推移.png
34.6KB
楽天証券_グロース株平均貸株金利推移.png
34.6KB
上記は楽天証券の2024年4月から2024年6月前半のグロース銘柄の平均貸株金利の推移です。
多くの銘柄で決算が集中するのが4月後半から5月中旬までですが、決算前に貸株金利が上昇し、決算後に貸株金利が下降し、また貸株金利が上昇して戻すという動きをしています。
SBI証券やGMOクリック証券も楽天証券と同じような傾向があります。
貸株金利の収集を始めてから分かったのですが、特に楽天証券は決算前後の貸株金利の変動が大きいです。
楽天証券では、決算直後に貸株金利を下げて、それからまた金利が戻るといった動きをすることが多いので、おそらく貸株の需要が読めないので、決算直後は予防的に貸株金利を下げているのではないかと推定しています。
続いて具体的な個別銘柄を見てみましょう。
 4375_セーフィー_貸株金利推移.png
34.2KB
4375_セーフィー_貸株金利推移.png
34.2KB
上記は「
4375 セーフィー 」の貸株金利の推移です。
セーフィーは2024年5月15日が第1四半期の決算発表だったのですが、楽天証券、SBI証券、GMOクリック証券いずれも決算前に貸株金利が上がり、決算後に下がるという動きをしていることが分かります。
決算時は信用買残の減少、権利取得のために貸株の供給が減る
これまでも述べてきたように、貸株金利は需給で決まるので、決算時は貸株の需要が強く、供給が弱い状況になっているということになります。
まず、供給面で考えてみると、信用買残による貸株の供給減があります。決算の数字次第で株価は大きく変動し、リスクが高いので、信用取引のポジションを解消しておくという動きが発生します。
リスク回避で信用買いだけでなく信用売りについてもポジション解消がされますが、ほとんどの銘柄は信用売残より信用買残の方が多い(買い長)ので、全体で見ると信用買残の減少によって貸株の需給はタイトになります。
また、決算時には、優待、配当、議決権を取得するために貸株を返済する動きがでます。
ネット証券で貸株サービスを利用している一般投資家の方も、ほとんどの方が貸株サービスに付随する便利な優待自動取得や配当自動取得機能を活用しています。
決算時はリスクヘッジの空売り、優待クロスの空売りで貸株の需要が強まる
先に述べた通り、株価は決算の数字次第で大きく動きます。
長期保有で株式を保有している投資家でも、決算による短期的な株価の値動きのリスク回避のニーズがあります。
リスクを回避する方法として、銘柄の空売りが有効となります。
また、日本株では優待に力を入れている会社が多く、多くの一般投資家の方が、株価変動リスクを抑えて優待を得るために、現物買い、信用売りのいわゆる優待クロス取引を行っています。
この優待クロスも決算期に特有の空売り需要となります。
以上に説明したような理由から、貸株金利は決算前に上がりやすく、決算後に下がりやすくなります。
証券会社側も本来決算期は貸株のトレーディングによる収益が得やすい状況です。そこで、SBI証券では、貸株サービスの機能で「金利優先コース」を選択し、特定の銘柄で権利確定日に貸株状態になっている場合、貸株金利1日分(権利確定日分)に対してボーナス倍率を適用するユニークなサービスを提供しています。
ボーナス倍率適用銘柄は
毎月アナウンスがされています。ボーナス倍率適用銘柄は優待の権利確定日に当たるケースが多いです。
配当もなく、優待も不要というケースでは、金利優先を選択しておくと良いかもしれません。
ただし、たった一日だけの金利なので正直あまり気にする必要はないかと思います。